火災予防情報
火災予防のための情報を紹介します。
住宅防火
「住宅防火 いのちを守る 10のポイント」を実践しましょう 。
4つの習慣
- 寝たばこは絶対にしない、させない。
- ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
- コンロを使うときは火のそばを離れない。
- コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。
6つの対策
- 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。
- 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。
- 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。
- 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。
- お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。
- 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。
「住宅防火 いのちを守る 10のポイント」リーフレット(PDF 310KB)
放火防止対策
火災の原因の上位に「放火」・「放火の疑い」があります。
放火をされにくい環境を作りましょう。

たき火による火災
近年、たき火が出火原因の上位となっています。
風が強い日や燃えやすいものの近くで行うと、思いもよらず燃え広がることがあります。

【実際にあった火災例】
・庭でたき火をしていたところ、風で火の粉が飛び建物が燃えた 。
・畑でたき火をしていたところ、火が衣服に燃え移って大やけどをした。
電気関係の火災
身近で便利な電気製品ですが、使い方や管理を誤ると火災につながる恐れがあります。
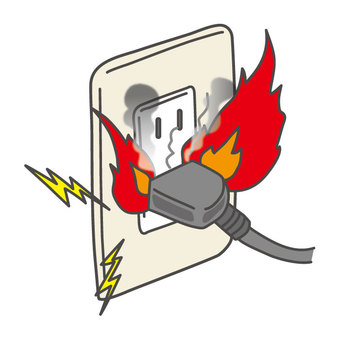
【実際にあった火災例】
・電気ストーブをつけたまま就寝したところ、掛布団が触れて火災となった。
・たこ足配線で多数の電気製品を使用していたところ、電源タップが熱を持ち出火した。
・電源コードを機器に挟んだまま使用して出火した。
・自ら電線をよって接続した延長コードを使用していたところ、ショートして出火した。
製品からの火災
説明書のとおりに使用していても、製品自体の不備により出火することがあります。
当消防本部管内でもリコールの対象となっていた電源コードから火災が発生した例があります。
事例や注意点などはこちらをご覧ください。
たばこが原因の火災
たばこが原因の火災が毎年多く発生しています。

たばこ火災を防止するため次のことに注意しましょう。
- 吸い殻は投げ捨てるなどせず灰皿を使用しましょう。
- 吸い殻は水につけるなど完全に消火しましょう。
- 吸い殻は灰皿に溜めずこまめに捨てましょう。
- 燃えやすい物の近くでは吸わないようにしましょう。
- 寝たばこをしないようにしましょう。
ごみ収集時のスプレー缶等による火災
近年、中身が残ったままのライター、スプレー缶等がごみに出され、ごみ収集車から火災が発生する事案が起きています。

ライター、スプレー缶等は必ず中身を使い切り、正しいごみの分別を行い、火災を防ぎましょう。
また、充電式電池(モバイルバッテリー等)による火災発生件数も増加しているため、注意しましょう。


